第21号:高収益・高賃金事業を実現していく販売会議のポイント
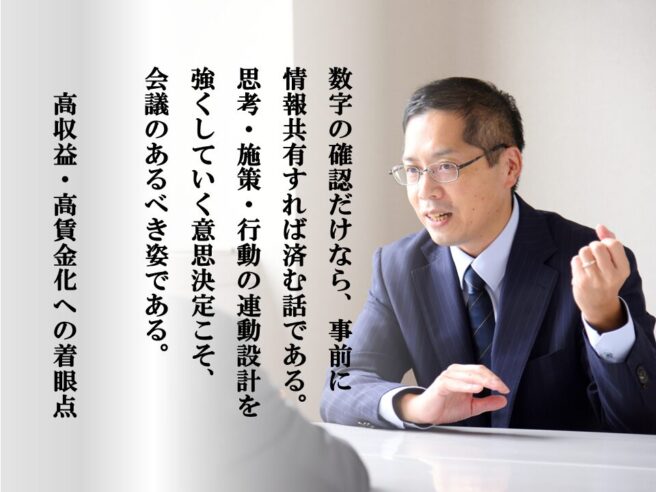
「シライ先生、営業指導の甲斐あって多少売れるようになってきました。けれど、どう考えても営業1人当たり5000万円の粗利目標には届かない状態です。」
高額な専門品を扱う小売業A社長は、そうご発言なさりながら、営業会議の資料をお持ちされました。そこには、向こう1年程度の注残、予測損益(前期と後期)、予測資金繰り表、今期実績表、前年予実対比表、そして当月引き合い案件情報があります。その資料の厚さに面食らう私でしたが、一通り目を通した後、気になることを社長に質問します。
「議事録と決定事項について拝見させて頂けますか?」
「メモ書き程度のものならありますが・・・」と仰るA社長。お伺いしてみると、入金状況の確認と督促、注残の変更情報、そして当月引き合い案件に対するアプローチについて簡単に決めた、というのが会議の決定事項だったようです。
販売に限らず会議とは問題解決と意思決定を行う場です。会議の場は年間目標を実現していくため、計画と事実の際を検証し、改善していくための中間ポイントになります。
A社は営業1人当たり5000万円という非常に高い粗利目標を掲げています。営業指導も多少の効果を上げていますが、とてもとても届くレベルではありません。現状を遥かに超えていく目標に到達していくには、社員教育の前に備えなければならない会議機能があります。それは「受注導線の設計と運用に関する仮説検証機能」になります。
受注導線とはこのコラムでも何度も紹介していますが、価値を落とさず確率の世界で売れる状態を作るために、認知獲得から商談成立までの流れを設計した情報網及びその運用の仕組みです。この導線がうまく機能しているかを検証し、次なる行動を決めていくことが販売会議の大きな目的になります。
価値を落とさず伝えきる販売活動には、受注導線という考え方が必要不可欠になります。高付加価値・高単価で販売し切るためには、統一されたメッセージをあらゆる場面で隙なく伝えきる必要があるからです。残念ながら、会議の中から受注導線の仮説検証機能ががっぽり抜け落ちている会社はことのほか多い印象を受けます。その理由は2つあります。
1つは、そもそも販売会議とは何をするべきなのかが掴めていないことです。うちは販売会議をしっかり運用している、という会社の会議資料を拝見すると、数字に関する資料が殆どだったりすることもしばしば。
もちろん数字資料が必要なことは言うまでもありません。しかし本来、数字資料というものは会議参加者が事前に確認しておくべき資料であり、当日に確認する資料ではないのです。数字はある時点での結果がどうなっているかを示す「静的」な情報にすぎません。
会議という機能は、そこに複数人の時間を投入するという意味で、時間当たりの「付加価値」を強烈に意識した運用が必要になります。その会議時間が生み出した「決定」が、会議後の人時生産性を高めていくものでなければ、会議を実施した意味がなくなります。つまり、重要なことは静的な数字の確認ではなく、会議後の「行動に関する決定」と「その実施計画」という動的な変化なのです。
もう1つの理由は、物事を連鎖連動させるという発想がないことです。先程申し上げたように、販売においては受注導線という連鎖連動の仕組みが必要となります。しかしこれに関する意思決定内容については全くないか、あるいは触れられていたとしても個別単発施策に対する協議が取り上げられており、施策間の連動という観点が抜け落ちていることが大半です。
顧客が購入・発注に至るまでには必ず、何らかの経路を通って成約に至るはずです。その経路を意図的に設計し、経路への流入や成約に向かって漏斗のように顧客を進ませていく過程を意図的に作ったものが受注導線です。受注導線がなければ、購入に至るまでのどこで詰まっているのか、どんな問題があるかの検証しようがないのです。
これにより結果的に何が起こるかというと、会議で話し合う内容が「当月引き合いの刈り取りに対する話」ばかりになるのです。まさにA社が陥っている状況そのものです。A社もHPやSNSを運用し、販売促進的なイベントを打っています。当然、これらの要素も販売に関連する受注導線の中の一部です。
しかし残念ながら、ここに「導線設計と連鎖連動」という発想がないがゆえに、それらを連動させて大きな売上を作っていける土台がないのです。そのため、受注手前の刈り取り部分の商談だけで数少ない引き合いをどうにかしようとし、多くの場合は「値引き」をして販売を着地させる、という何ともつまらないやり方で受注することになります。
販売会議でやるべきことは、受注導線という仕組みの「改良改善」または「廃止新設」に関する検証と意思決定をすることになります。既存の導線上でやり方やメッセージを変える決定をする、あるいは今までにない新しい導線を敷く、あるいは成果を上げられなくなっている導線の見直しを検討する。こういったことについて、現場を担当している社員からの報告や提案を基に意思決定することが、高付加価値販売を実現していく販売会議のあり方になります。
導線全体に関わる会議になるわけですから、その出席者についても変わってくるはずです。受注に近い側での商談を担う営業と、受注導線全体をサポートする販売促進が連動していなければ、個別単発の議論に終始してしまい、メッセージの一貫性と施策の連動性が確保できなくなります。
連鎖連動という発想は高収益・高賃金企業を作っていくうえでの重要なキーワードの1つです。思考の連動・業務の連動・行動の連動を通じて、大きな付加価値を作り、守りながら伝えていくことができれば、着実に目指す水準に向かっていくことが可能になります。その中でも特に重要になってくるのがこの受注導線という連鎖連動の仕組みであり、その仕組みを運用していく要が販売会議になります。
「そういえば色々と販売促進についてもやってきているつもりでしたけど、いつも当月刈り取りの話で終わってしまうことが多かったです。非常に勿体ないことをしてきましたね。まず当社の場合、受注導線の設計からしなければならないでしょうか。たたきがなければ導線に関する話し合いもできないですからね。」
A社長はカバンからA3サイズの用紙を取り出します。そして自らペンを動かし、そのキャンパスに受注導線の設計図を描き始めました。
コラムの更新をお知らせします!
コラムはいかがでしたか? 下記よりメールアドレスをご登録いただくと、更新時にご案内をお届けします(解除は随時可能です)。ぜひ、ご登録ください。

