客観的評価を受け入れ、「伝え方」を考える
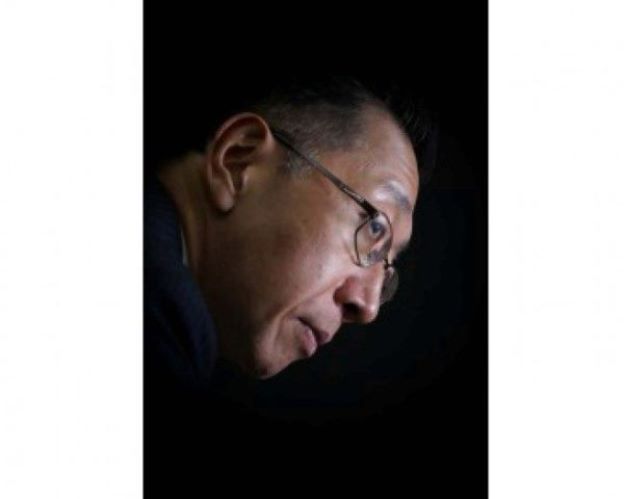
「後藤さん、この本を読ませてもらって、この原稿を後藤さんが直接書かれたのなら、非常に完成度の高い原稿を出されたと思いました。ただ、本のタイトル・構成・見せ方を工夫しアレンジすればもっと良くなると思いますよ。」
これは、先週、出版社の方に私の本について相談をさせてもらったときに、その編集者の方が私の本を読んで私に話された内容の一部です。
2冊目の本を出版するかどうかは未定ですが、客観的に自分の著作本について評価をいただいたことは非常に参考になり、一度企画案を出版社の方にご提案いただくことにしました。
ここで私が言いたいことは、私が本の出版を検討しているということではなく、
- 自分がやったことに対し、第三者の客観的な 評価をしてもらうことがとても大事。
- 同じ内容でも、見せ方や「顔(タイトルなど)」が変われば、印象や評価も変わる。
ということです。
私も、仕事で中小企業の経営力の評価をさせていただくことがあり、そのために経営者へのヒアリングをさせてもらうことがありますが、(全てではありませんが)周りが見えず、自分の中での評価・見解だけで事業を進めようとしている経営者もおられます。
「競合他社は存在しない」
「他社にはない」
ということを力説される経営者の中には、実は競合やベンチマークとなる企業を知らないか、「見ようとしない」方もいらっしゃるということです。
また、チラシ一つとってもキャッチコピーやデザインが変われば、同じ内容が書かれていても印象が全く変わります。
例えば、
「1000mgのビタミンC」と
「レモン〇〇個分のビタミンC」とでは、
どちらがお客さんは買うか?といったことです。
知的財産でいえば、商標や意匠・著作物をどう活用するかということとつながります。
外部環境を知り、第三者の客観的な評価を受け入れること。
買ってほしい人に「伝わる」伝え方は何かを考えること。
大事ですね。
コラムの更新をお知らせします!
コラムはいかがでしたか? 下記よりメールアドレスをご登録いただくと、更新時にご案内をお届けします(解除は随時可能です)。ぜひ、ご登録ください。

