研究開発と営業マーケティングの順番と相互乗り入れ
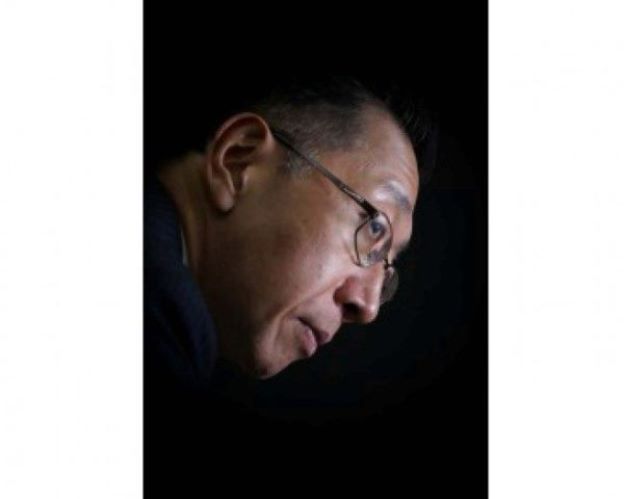
「後藤さん、当社では新事業展開のための研究開発を進め、特許も数件出願しているんですが、これらの特許が本当に事業に活かせるかどうかがよくわからないんです。研究者はすぐに出願すべきと言うんですが、費用も掛かりますしね・・・」
これは、先日ある会社で特許や契約に関わる相談を受けたときに、その会社の役員の方が仰った言葉です。
その会社では新しい技術の開発を進めておられるのですが、その用途開発をどうすべきかでお困りの様子で、特許取得の費用対効果にその役員は疑問をお持ちのようでした。
私からは、一度出願担当の専門家、研究者及び経営者で、事業のビジョンと特許の活用を改めてベクトル合わせした方がよい旨、お話しさせていただきました。
このコラムでも何回も申し上げ、また今回も申し上げますが、開発の成果として特許を取得してから用途を探すのは、順番として逆です。
特許活用における典型的な失敗例です。
お客様が誰で、そのお客様にどのようなモノを提供するかがあって、そのモノに独自性を付与し、差別化するために特許を取得するという流れでないと特許の活用はできません。
また、「営業と研究は別の人種」という言葉もよく聞きますが、この考え方では、研究者の研究意欲が単なるエゴになり、営業は説得力のある販売促進ができなくなり、営業と研究にさらなる乖離が生じてしまいます。
製造業やサービス業では、「売れる」「お客様に喜んでもらえる」ことが前提で研究開発をすべきですし、営業もセールストークする上で、最低限の技術知識(どの技術を使えばどのような効果があるのか)を知らないとお客様に説明できないですよね。
研究開発と営業・マーケティングは一体不可分にならないといけないということです。
研究開発と営業・マーケティングの順番を間違えないことと、双方の相互乗り入れを進めることです。
それにより知財活用が可能となる体制が作れるのです。
コラムの更新をお知らせします!
コラムはいかがでしたか? 下記よりメールアドレスをご登録いただくと、更新時にご案内をお届けします(解除は随時可能です)。ぜひ、ご登録ください。

