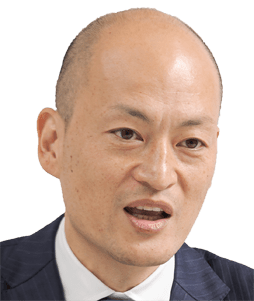社長が押さえておくべき「武術」と「経営」の共通点

先日、ある経営者の方から武道と武術の違いについて教えていただきました。武道は決められたルールに則って、スポーツとしてその技を競うもの。一方、武術は実戦の場において相手に勝つ、正確に言うと相手に負けないための術を身につけるものだと。
武道のように、「蹴りはなし」とか「金的攻撃は反則」などと言っても、実戦の場においては相手はそのようなルールには従ってくれませんから、武術においてはこちらもなんでもありが前提となる。
しかし、武術はなんでもありだからと言って自由に手を繰り出せばいいわけでは決してなく、基本の「型」をしっかり体得しなければ、力が分散したりして相手に効果的なダメージを与えることができないとのこと。
これは経営においても全く同じことがいえます。過去の日本は政府や業界団体による規制だらけで、特定のルールに守られた「武道」的な業界も多かったですが、いまやそういった護送船団式な規制は外圧によって次第に取り払われ、またITとプラットフォームの進化によって異業種からの参入もどんどん容易になっていっていますから、まさに「武術」が想定しているように「なんでもあり」の様相を呈しています。
また、消費者のニーズもますます多様化し、またその流行のサイクルもどんどん短くなってきていますから、顧客からの要望も「なんでもあり」的に目まぐるしく変わっていきます。
しかし、その多様な要望に対して自由に、そして場当たり的に対応して業務を進めていたのでは、これも武術と同じでまったく効果的・効率的な仕事になりません。
つまり、会社が競争力を出していくためには、個々の社員が自分の仕事を好きなやり方でこなすのではなく、会社として基本の「型」を設定する必要があります。これが、仕事を仕組みで廻すということです。
一見毎回内容が異なっているように見えるお客様への対応も、視点を上げて見比べてみれば共通点は数多くあることに気づきます。その部分を「型」として標準化しておけば、数をこなせばこなすほど仕事の質や効率性は上がっていきます。これは製造だろうが、受注対応だろうが、営業だろうがすべて同じです。
もちろん、標準的な「型」では対応しきれず、個々のケースで調整が必要な部分が生じます。ここはクリエイティブな要素が求められる部分です。これも、基本的な部分を「型」で対応していれば、労力をこのクリエイティブな部分に集約させることができますから、仕事の完成度は格段に上がります。
言うなれば、オーダーメードのスーツを受注し、フルオーダーではなくイージーオーダーで仕立てるようなものです。あらかじめベースの型紙が用意してありますから、その部分は一からデザインを起こす必要がなく、ギャップがある部分を調整すればいいということです。当然コストも時間もフルオーダーでやるより少なくすみます。
社員を型にはめることに抵抗があると経営者に言われたことがあります。しかし、フリーハンドで自由に社員に仕事をさせることが、本当に彼らにとっていいことでしょうか。これは武術を習いに来た生徒に「好きにやっていいから」と実戦に放り込むようなもの。OJTと言えば聞こえはいいですが、単に放ったらかして何も教育しないとことと同じです。
「守破離」という言葉がありますが、まずは「守るべき型」があってこそ、その進化のプロセスとしての「破」も「離」も起きてくるということです。
もちろん、一度決めた「型」でずっと通用するということはありません。数百年の歴史を経ている武術の「型」は完成形として確立されているでしょうが、仕事の「型」は顧客ニーズの変化や業務内容の変遷、社員のレベル向上に合わせて常に見直していく必要があります。
そして重要なことは、「守」として仕事の型を決めることも、「破離」としてその型を進化させていくことも、個々の社員任せではなく、経営の重要取り組みとして会社が主導して行うことです。
個々の社員が勝手な型をつくり、それが見える化・文書化もされず個人の頭の中だけにとどまり、そしてそれが相性のいい部下や後輩にだけ伝承されていく。そんな状態になってしまっては、組織としての強さは一向に生まれません。社内で様々な他流試合のぶつかり合いがおこなわれるようなものです。
型を整えることも、その型を壊し進化させていくことも、重要な経営上の取り組みとして会社主導で行っていきましょう。
最後に談志師匠の言葉を紹介して締めとさせていただきます。
『型ができていない者が芝居をすると形なしになる。メチャクチャだ。型がしっかりした奴がオリジナリティを押し出せば型破りになれる。どうだ、わかるか?』
コラムの更新をお知らせします!
コラムはいかがでしたか? 下記よりメールアドレスをご登録いただくと、更新時にご案内をお届けします(解除は随時可能です)。ぜひ、ご登録ください。